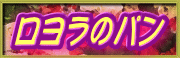◆HEART IS GOLD・「ロヨラ」ある芸術家の青春の断片
★UP DATE 2003.03.07



この作品は、2003年1月4日未明に逝去した芸術家ロヨラ氏(仮名)の追悼作品です。
生前のロヨラ氏を偲び、心よりご冥福を祈ります。
そして、この作品のみ、ロヨラ氏の生前親交があり、認め合っていた方々にのみ、
参考資料として、この作品の引用を無料で許可します。
今年はロサンゼルスでオリンピックがあった。知らないうちに俺が大阪の南河内にある大学で暮らし初めて2年半が過ぎた。この冬、昨年の春から一年間ベーシストとして参加していた「シーナ&ロケッツ」「アン・ルイス」「松田聖子」などのカバーバンド「G&B・モンスターズ」が解散し、メンバーはそれぞれが新しい道を歩み始め、俺はバンド浪人中だった。
柔らかい秋の午後の陽射しが差し込む教室で、俺はいつものようにパンクスの格好で居眠りしながら「芸術学概論」の講義を受けていると、後ろの席から小声で、
「うおるふぃー、うおるふぃーっ、うおるふぃー!」
うっとうしげに振り向くと、声の主は同じクラスの顔見知りのテルだった。俺の隣の席に置いたド派手にいろいろなステッカーが貼られたケースを指さし。
「君、トランペット吹くんかい?」
「ああっ」
うつろな意識の中、生返事をした。
「あとでセッションしょーや!」
「・・・・・・ああっ」
講義が終わり、俺とテルは小高い丘の上に打ちっ放しのコンクリートのビルが建ち並ぶ、殺風景ながらも奇抜な大学キャンパス内の12号館の最上階の一室に向かった。そこがこの大学のJAZZ研究会のクラブハウスだった。
既に遠くから少しづつ楽器の音は聞こえており、教室の黒板の裏側にある三角形の間取りのクラブハウスは、手前が応接・鑑賞・喫茶スペースで、奥へボーカル、コーラス、ホーンセクション、アップライトピアノ、キーボード、ギター、ベース、そして一番奥にドラムセットとパーカッションセクションという配置になっていた。
「ぬひょ、ぬひょ、ぬひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょっ」
一番奥のドラムスに目をやると、そこには奇声を上げながらミリタリー風の迷彩服を着た男がドラムスを叩いていた。ド派手にシンバル・タムなどを鳴らすプレイが目立つが、しかし、ドラムスの基本中の基本バスドラム・スネアドラム・ハイハットワークもしっかりしている。
「只者ではないな・・・・・」
その男の名は「ロヨラ」、今思えば、これが運命の出会いだった。
テル意外のそこにいたメンバーは、キャンパス内で顔は見たことはあるが、何者か分からない存在だったので軽くそれぞれ自己紹介を行い、いきなりスタンダードナンバー「Fのブルース」からジャムセッションが始まった。
バンドの編成は、俺とテルのツイン・トランペット、クラス内ではあまり話をしなかったテルも、トランペットをやっていたのには驚かされた。テナーサックスのチャーリー、ギターのジョンとジェット、ピアノのビル、ベースのユキ、そして、ドラムスのロヨラというその場にいた寄せ集めの編成だった。この時俺はFのブルースという曲は知らず、頭の中で勝手に「FーB♭ーCで展開するブルースだな」と勝手に解釈しながら適当に演奏していた。ハッキリ言ってこの時が、本格的なアドリブ演奏の初体験だった。その段階で俺は知らないうちにJAZZ研究会のギターのジョンが率いるチャーリー、ユキ、ロヨラが所属するバンド「J&B」に入れられてしまった。
俺達がいた南河内の大学の学生は大きく分けて2つの人種に分かれていた。何処までも内面追求を行い、外部からの吸収・凝縮により創造を行う人種と、内なるエネルギーを外に発散し己と他のぶつかり合い、破壊・融合により創造を行う人種であった。あの当時は俺もロヨラもどちらかといえば後者の人種かと思われていたが、今考えてみると前者的要素も多く内面的にあった。そして、当時の他の大学と決定的に違うところは、普通の格好をした学生に対する比率に対し、パンクス・ヘビーメタル・コスプレヤーズなどの「傾奇者」の比率が高かった。俺は日本の有名なロックンローラー忌野清志郎氏、世界的に有名なパンクバンド「セックスピストルズ」のベーシスト故・シド・ビシャス氏風コスプレでキャンパスを闊歩すれば、ロヨラ氏はミリタリー、甲賀忍者、月光仮面のコスプレで普通に講義を受けていた。俺たちのグループとは関係ないが、お昼休みにキャンパスにラジカセを大音響でかけながら、白いヨーロッパの貴婦人風?の衣装に身を包み、白い日傘を持って松田聖子さんの「白いパラソル」を踊るストリートパフォーマーのオカマ野郎もいた。(後に学園祭の時振り袖を着て、JAZZ研究会のコーナーにやって来た。)ここまでこの大学に傾奇者が集まってしまったのも、あのお方達の影響だろう。あの方々の・・・・・。
新学期、五月中旬に学内で行われる五月祭のオーディションに向けて、J&Bの活動も本格化してきた。J&Bには学内でも本当に個性的な奴らが集まった。俺はパンクス風の傾奇者、ジョンはベビーフェイスのプレイボーイ、チャーリーはオッさん、ユキはシロクマ君、そして一番問題のロヨラは、なんと例えたらいいんだろうかムムムッ・・・・・、外見的はミリタリー?甲賀忍法伝承者?日本の1990年代のコミックス「るろうに剣心」に登場した将軍直轄の忍者集団御庭番衆お頭「四乃森蒼紫」?。内面的性格は1983年公開されたアメリカ映画「アマデウス」の主人公W.A.モーツァルトを演じた「トム・ハルス氏」?、日本の漫画「ドラゴンボール(1987〜1997年)」の主人公「孫悟空」?にあえて強引に例えれば似ている。
彼が当時行っていた活動、ドラマー・デザイナー・漫画家などの作品を鑑賞すると、どの作品も外見の第一印象は「なんだこれは!!」という衝撃を受ける。中身も思考回路も天才的で、常に理論的なものと感覚的なもののバランスが良く、時々俺以上に傾奇者になり一緒になっていろいろとバカな事をやっていました。例えば当時、かなり多くの少年少女達に影響を与えていた「北斗の拳」をモチーフにしたギャグ・セリフ・必殺技などを自分なりに作品の中に転化したり、突然みんなを笑わせたり、妖しい感じを演出したり、常識や既成概念に囚われない自由な発想を持ちながら理論的な表現ができ、新しい時代を創造出来る天才的な芸術家だった。
それ故に、20世紀中の腐った日本の学校教育にマインドコントロールされた「大馬鹿野郎!!」には理解されなかったが、彼の下にはのちにインターネット上でそれらの価値観に疑問を持ち、共感する者達が集まった。しかし、もうロヨラはそんなイデオロギーの争いとは関係のない次元に旅立ってしまったが・・・・・・・・・もしかしたら今頃、向こうでもその争いは続いているかな?この世のものより遙かに高い次元で。俺もこの世の次元では絶対そいつらに屈することはない!!どっちが正しかったか、もうその答えは21世紀を迎えた2003年時点での日本の行き詰まった状況を見れば理解できるでしょう!!! しかし、多くの人々がまだ気づいていないかもしれないが、現在目の前にある問題の解決策も、そのすぐ隣にあります。今でもロヨラが普段から叫んでいた
「ぬひょ、ぬひょ、ぬひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょひょっ」
が今も耳から離れない。
大学の講義・アルバイトが終わっても、当時俺達は住所があったコーポ・学生寮に戻ることは少なくなり、俺とロヨラとJ&Bのメンバーは、クラブハウスでのセッション終了後、夜中に自動車で奈良県の天理市にまでニンニクがたっぷり入った名物ラーメン「天理ラーメン」を食べに屋台に出かけたり、大阪・堺・神戸・京都市内の夜の町を徘徊し、たこ焼き、お好み焼き、うどん、焼きそばを食べ歩いたり、本流のジャズ喫茶に出かけ、真空管アンプから流れる古いジャズと熱いコーヒーを堪能し、真面目な事からバカな事まで一晩中いろいろ語り合った。例えば、
「ヘイ!うおるふぃー!!クリスマスになると、西洋では、メリーさんは、寂しくなるらしいよ!!!」
「なんで?」
「メリーさん! メリーさん! メリー、クリ〇〇ス・マス〇ー〇―〇o〇!! だよーーーん!!!」
「・・・・・・・・」
(〇の部分を入れてしまうと、日本国内外で放送禁止用語になる恐れがありますので、割愛させていただきます。どんな言葉になるかは皆様のご想像にお任せします。想像できる単語が全員同じであったとしても、その想像の責任は当局では一切関知いたしません。)
〇の部分を強調し表現したらドット笑いが起こり、一晩中みんなでそればかり「ぬひょぬひょ」と叫びまくり、後に新しいクリスマスソングが一曲出来上がった。(この内容も「よいこ」には危険すぎますので、割愛させていただきます。)
後日、五月祭のオーディション曲が決定し、ジョンから発表された。スティービー・ワンダー氏のオリジナル「アナザー・スター」を、日本のクロスオーバーバンド・ギターワークショップのアレンジ版で、それをさらにJ&B風にアレンジしたものを創造する事になった。この曲は、ギターソロをフューチャーしたラテン系の曲だったので、ロヨラはパーカッション・お囃子・かけ声を担当し、アフリカンテイストへの回帰を図った。
本当にロヨラの発想・作品には時々ドキッとさせられることがある。例えば漫画、俺が鑑賞した作品で今でも強烈に印象に残っているのが「チャーリーの拳」、テナーサックスのチャーリーを主人公に「北斗の拳」をパクッた四コマ漫画で、一見残酷に見えるが流石!関西人!!お笑いを忘れちゃいなかった!!!リアルな描写とシニカルなブラックジョークは、主人公にされたチャーリー自身も否の打ち所のない作品だった。そして音楽、ドラムス・パーカッション、ロヨラも俺もJAZZ研究会に身を置きながらあらゆる音楽・芸術の可能性を否定しなかった。後に頭の固いビルに煙たがられる結果となったが、自分に正直に、やりたいよーに俺もロヨラもやっていたので後悔はしていない。やっていた音楽がJAZZだったからこそ、あらゆる可能性を認め、新しい事が出来たんたろう。しかし「アイデンティティー」はしっかりと根底に持っていた。世界中の中途半端にお偉い方々に共通し言える事だが、俺たちのような下々の者たちが「アイデンティティー」を持つのが嫌いらしい。ハッキリ言って、中途半端に偉いだけじゃ、下々の者達にどんなに威張っても、笑われるだけだけど・・・・・。笑われたくなかったら、下々の方々も納得・尊敬できる目標を持って、物事に臨んでください。
俺とロヨラが共通で好きだったアーティストは、世界最強のロックンロールバンド「ザ・ローリングストーンズ」。今思い出してみると、ロヨラのドラムス・パーカッションワークの根底には、傾奇者の対局の座標に位置する「自然体のドラマー」のチャーリーワッツ氏のプレイスタイルが染みついていた。俺自身も演奏中たまに「内面的傾奇者」キースリチャーズ氏が入ってくる事があった。後に俺とロヨラ・ユキ・ジェットでブルースバンド?「スナイパー」を結成し、ザ・ローリングストーンズ、ジミ・ヘンドリックス氏の音楽などをカバーした。スナイパー中でもたまにアドリブセッションを行い、そこで俺の奥義クラスの技のひとつ「パンキッシュイタコ風チャネリングボーカル」をロヨラが弾き出すリズムにより開眼した。
そしてオーディション当日、オーディションはJAZZ研究会のクラブハウスの隣の14号館の大講堂で行われた。普段この講堂は、各学科共同の一般教養科目「保健体育」の講義などで使用される(2003年現在では、日本を代表するマラソンランナーだった増田明美さんが教鞭を振るっているものと思われる)。講堂は約300人ぐらい収容可能だが、音響は最悪だった。オーディションのエントリーバンドは約50バンド、その中の5バンドがキャンパス内のドレミの広場のステージ、五月祭舞台を踏むことが許された。
参加バンドの多くはドラムス・ベース・ギター・ボーカルが基本で、オプションによりサイドギター・キーボード・コーラスなどが入る典型的なロックバンドが殆どで、たまにソロの生ギターの一発弾きの者も居たが、ホーンセクション・パーカッションセクションを備えた大所帯のビッグバンドはJ&Bだけだった。オーディションのエントリーナンバーは32番、観客の殆どがライバル、その中でも俺たちは「異色」な存在だった。そしていよいよJ&Bの出番が廻ってきた。
「エントリーナンバー32番、J&B、曲はアナザー・スター」
素っ気ない司会者の紹介後、一瞬の静寂が会場を包み、エレクトリックドラムを交えたラテン系アフリカンテイストの呪術的なロヨラのパーカッションとお囃子「アーウウッ、アーアーウウッ」から演奏は開始された。そこにジュンのスピード感のあるビートドラム、ユキのゆったりとしたアルペジオベースのフレーズが絡み、俺とチャーリー、後に加入したトロンボーンのイッちゃんからなるホーンセクションが絡み、ジョンのパワフルで流れるようなギターソロによる主題が始まった。既にこの時点で会場の奴らは、
「おや、今までの出場バンドとは違う!」と、感じられたせいか注目を集めた。
ワンコーラス終了後、ドラムのジュンとロヨラのパーカッションソロの掛合いからアドリブタイムは始まり、各自が思い思いにアレンジしたソロを取った。もうプロレスで言うと場外乱闘状態で、皆が日本のコメディアン集団「大川興業」のように、好き勝手に叫び!傾奇!暴れ!騒ぎ!まくった!! その時点で既に会場では、手拍子どころか、世界的に有名な曲だったので、俺たちの新しいアレンジに度肝を抜かし、酔いしれ、踊っている奴らもいた。それをまとめる形で再びロヨラの「ワン・ツー・スリー・フォー!!」のコールにより全員参加のユニゾンのコーラス、
「ラアーラッラララァーララッラアーラアーラララアーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーッ」
が、かけ声
「ドリャーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!!」
を伴い繰り返された。そしてジョンのギターソロによる主題に戻り、フィナーレへと雪崩れ込んだ。エンディングのサビが終了すると、万雷の拍手が巻き起こった。
「このオーディションの中で、バトルを越えて観客を一番楽しませたのは俺たちだ!!」という手応えを感じた。
しかしオーディションの結果は落選。ハイレベルなバトルであったのと同時に、審査員の固定概念をブチ壊すまでに至らなかったのが敗因だっただろう。技術的には後日、その時の演奏テープを聴いてみると、人数が多すぎてまとまりが取れなかったせいか、ギター・キーボード・ベース・ドラムス・パーカッション、ホーンの各セクションのあいだに微妙なズレが感じられたことは否めなかった。このオーディションで合格した5バンドでさえ、のちにメジャーになった奴らはいなかった。なったらなったで、また大変だったかもしれないけど・・・・・。
五月祭のオーディション終了後、J&Bにはダラダラした日々が続いた。今考えてみると、この時ジョンやロヨラを焚きつけて、内面を磨き、対外的にもっと頑張っていればアメリカのバンドで「アース・ウインド・アンド・ファイアー」日本のバンドで「スぺクトラム」「米米クラブ」「東京スカパラダイスオーケストラ」タイプ?のバンドとして、メジャーへの道が開けていたかもしれない。しかし、もともと個性が強い面々が揃い、それをまとめるには11人というJ&Bのメンバーの人数は多すぎた。俺自身も現実は甘くなく、本業中の本業の大学の講義の受講と、生活のためのアルバイトが忙しく、その夏休みの瀬戸内海の小豆島の合宿までは、クラブハウスともう一つのたまり場の美術学科の校舎の屋上でJAZZ研究会のメンバーとフリーセッションしたり、おもちゃのピストルなどで、しょーもない「危険な遊び」で遊んだりするダラダラした日々が続いた。
夏休みが終わり秋、J&Bは再び一一月の学園祭に向けて活動を本格的に再開した。今度は女性ボーカリスト・aikoちゃんを迎えて、映画「ローズ」でペッド・ミドラー氏が歌っていた「男が女を愛する時」をカバーすることがジョンから告げられた。その時リードボーカルを担当したaikoちゃんは、一見何処にでもいる普通の女の子だったが、歌い始めると神懸かり的な強烈なオーラを放つ不思議な力を持ったボーカリストだった。その神懸かり的なところが、俺のパンキッシュイタコ風チャネリングボーカルとマッチして、フリーセッション時よく二人で「天昇」した。その時、俺たちの後ろでいつもドラムスを叩いて居たのはロヨラだった。
そして今回は間違ってしまえば大きくはずし、完璧な演奏が出来れば大当たりする。音楽的にギャンブリーな「バラード」をプレイすると言うことで、新しい試みであったため、いろいろ不安があった。当時大阪にあったバンドの中でも、J&Bと同じタイプのバンドは無く、かなりインパクトはあった。しかし、大きな問題がひとつあった。今までこのメンバーで多くのカバー曲の演奏、アドリブセッションをこなしてはいたが、しっかりした形のオリジナル曲はしたことがなかった。メンバーの中には優秀な作曲家・オリジナル曲を持った者も多く居たが、皆一人一人個性が強く、意見がまとまらず結局カバー曲のアレンジに留まり「これがJ&Bのオリジナルだ!!!」というものが打ち出せなかった。
そして10月中旬、再び14号館で行われた学園祭のオーディション、五月祭のオーディションで既にJ&Bの存在は学内知れ渡り、ビートルズの「Get Back」、U2の「Where the street have no name」のプロモーションビデオような野外ライブが可能なキャンパスの大通りを見下ろす場所にクラブハウス・練習場があったので、そこで毎日俺とロヨラ、J&B、JAZZ研究会の面々は思い思いのパフォーマンスを行った。当然J&Bは注目の的になっていたと同時に、ライバル達の「呪」の的にもなっていた。(この当時、現在ほど呪に対するディフェンスは万全ではなかった。)いま考えてみると、俺たちが通っていた大学には創作の形だけでなく、音楽的にも大きく分けて二つの流派があった。ひとつは音楽学科・演奏学科・音楽教育学科などの「クラシック」をベースとした流派、表面的には否定する奴らも居たが、深層心理的にはTWISTにあこがれて入学し「ロック」をベースとした流派が存在した。俺とロヨラは間違いなく後者の流派であったが、JAZZ研究会は後者に行き詰まりを感じ、その年に発生した「第三勢力」であった。どの世界でもそうだが、そのような新興勢力には既存の勢力は甘くなかった。演奏・パフォーマンス・知名度は五月祭の頃に比べ大きくレベルを上げたが、学園祭オーディションの結果も落選。やはり、先に記した通りこの半年の間にJ&Bのオリジナル曲を打ち出せず、もう一歩踏み込んだバンドとしてのスタイルが確立出来なかったのが敗因だろう。
再びJ&Bにはダラダラした日々が続き翌年の春、ジョンの卒業をもってJ&Bは解散した。その後「正統派のJAZZを守りたい」ビルと、「JAZZをベースに添えて新しい音楽を創りたい」という意見の違いから俺とロヨラはJAZZ研究会を去った。
俺がこの大学卒業してから数年後の夏、再びJAZZ研究会のクラブハウスを訪れたら、クラブは存続している様子が感じられたので安心した。この時キャンパス内には誰もいなかったが、クラブハウス前のキャンパス大通りを見下ろすベランダと、公式に演奏することが無かったドレミの広場のステージに立ち、旅行用にいつも持ち歩いている「ギタレレ」で、蝉の鳴き声を伴奏に「男が女を愛する時」などを演奏した。
JAZZ研究会退会後、俺はトランペットとギターを持ってストリートへ、ロヨラは「M・ブラザーズ」というコミックバンドに加入した。当時南大阪の山奥にあった彼らの練習場にたまに遊びに行くと、そこでのロヨラはJ&B時代よりも伸び伸びと自由に音楽、ギャグ、コスプレ、芸術を楽しんでいた。M・ブラザーズのメンバーは、ドラムス&尺八のロヨラ、ロヨラと同郷のベーシストのフォックス、紅一点キーボードのゆうこ、リーダーでギターのシゲル、ボーカルのアリの5人編成で、1982年頃シゲルとアリにより結成され、2003年時点でもシゲルとアリを中心にメンバーチェンジを繰り返し、活動しているらしい。(このバンドのホームページがあるが、現在行方不明。シゲル殿、アリ殿、このホームページを見ていたら連絡ください!待ってます!!)
M・ブラザーズでは当時、既にシゲル氏とアリ氏を中心に多くのオリジナル曲が創られ演奏されていた。その音楽の多くは、コミックバンドで演奏するのがもったいないくらい完成度の高いロックとポップスで、「超真面目な音楽」と「コテコテの大阪のギャグ」を追求しきったパフォーマンスとのギャップが、ステージ上で異彩を放ち、多くの人々を引きつけ、日本のインディーズバンドでは珍しく、今までの21年間生き残れたのだろう。そこでのロヨラは、音楽の合間のMCの「間」をコントロールするパートも任され、文章で表現するのは難しい事だが、音楽からギャグに移る際の「気」の流れの変化に凄いものを感じた。この感覚を感じたとき、武道で例えたら「命の遣り取りの現場・真剣勝負的」な気の流れを感じた。
ギャグの編成は、シゲルのツッコミと、ロヨラとアリのツイン・ボケ、フォックスとゆうこは基本的にはこの三人の遣り取りを一歩引いたところから見つめ、ピンポイントアタックでシゲルと共にツッコミを入れるパターンが、吉本新喜劇の芝居の流れのように決まっていた。
M・ブラザーズのパフォーマンスを俺は、大阪をあとにするまでのほぼ一年間見てきた。「ステージ上にありながら自然体で、ストリートを感じるバンド」だった。その感覚がバンドの善し悪しを決定し、すぐに消えるバンド、何年も続くバンドの差をこの時初めて実感した。どんなジャンルにも言える事かも知れないが、「周りをしっかりと見極めて、その気の流れを掴み、読み、その気に流されず、己の存在の自然体を保ちながらアイデンティティーを確立し、己を磨いて行くことが、継続の秘訣」であることを感じた。20世紀までの狭い範囲内での時の支配者にとっては、下々の民衆や個人が「自然体であること、アイデンティティーを持つこと」は、最大の邪魔者だったかも知れないが、21世紀を迎えた今、世界中に高速交通網・高速通信網が発達し、狭くなったこの地球の上では、「自分は何処から来た何者であり、これから何処へ向かうのか」という説明が出来なければいけない。「自然体を保ち、確固としたアイデンティティーを持って居なければ」何も出来なくなるだろう。そんな「自然体とアイデンティティー」を持っていたM・ブラザーズの演奏を、いつの日かまた聴いてみたい。もうそのステージにロヨラが居なくても。
大学卒業後、俺もロヨラもそれぞれの田舎に帰り、俺は数年間の就職浪人後新聞記者に、ロヨラは農協職員、テーマパーク社員、パン職人などをやりながら、年に一度年賀状で近況を報告しあった。年賀状が届くたび、「おっ、頑張ってるな」と、お互い感じながら。
そして俺は1999年2月に自分のホームページを立ち上げた事を葉書で知らせ、ロヨラも2000年9月に自分のホームページを立ち上げた事をメールで知らせてきた。当初ロヨラは、「闇の芸術家ポルポト」というホームページを立ち上げていたが、あまりにも内容が危険過ぎたため、各方面から攻撃を受け、閉鎖した。それ以降の出来事は、ロヨラのホームページ「ロヨラのパン」「ロヨちゃんネル」「RUハンターミツルギ」。そして俺のホームページ「うおるふぃーの芸術世界征服前線基地」に記してあります。ご覧になってみてください。
そして別れは突然やって来た。最後にロヨラと俺が交わした会話は、2003年1月1日のロヨラのパンの掲示板での
「うおるふぃー先輩!新しいクリスマスの挨拶何でしたっけ?」
「メリーさん、メリーさん、メリークリ〇〇ス マス〇ー〇ー〇o〇だよ!!」を外来語は使用せず、日本語に訳して答え、同日のロヨちゃんネルの掲示板の酒田市近辺の古典芸能の話をした。その三日後に起きる悲劇も知らずに・・・・・・・・・・。
2003年1月4日午後10時半頃、俺は寝室でいつものように一編の詩をしたためた。
「歩きだそう」 WORD by WOLFIE
澄み渡った空
蒼い月が輝く夜
吹雪は止んで雪原を照らし出す
山脈(やまなみ)は藍色に映し出され
時が止まったように何も聞こえない
このまま安らかな時が続いてほしい
もう白い闇の中で生きるのは嫌だ
白い闇は暗闇
暗闇は白い闇
陰陽交わる冬の夜
そこが黄泉の国への入り口のように
突然口を開けてくる
そこで眠ってしまったら
もう永遠に目覚めることはない
歩きだそう
吹雪が来る前に
歩きだそう
月が沈む前に
歩きだそう
雪に道が消える前に
歩きだそう
歩きだそう
歩きだそう
WOLFIE―JAPAN2003(C)
2003年1月8日午後8時頃、いつものように俺のホームページにリンクを貼らせていただいている方々のホームページをチェックしていると、ロヨラのホームページに異常を感じた。掲示板の書き込みを覗き込むと「ロヨラが死んだ」と記されていた。
始めは悪い悪戯か、日頃から狙われていた「ネット上の敵」へのカモフラージュか?と、思っていた。しかし、ロヨラのホームページにリンクを貼っている方々の掲示板も覗いてみると、同じ話題だった。
「悪い冗談だろ!」と思いつつ、胸騒ぎが拭えなかったので、翌日の1月9日、大学卒業後初めてロヨラの家に電話した。
「もしもし、大阪の大学時代の友人のうおるふぃーです。ロヨラ君はいらっしゃいますか?」
受話器の向こうにはロヨラの奥さんが居て、その向こうには無邪気に遊ぶ彼の幼い次男の声がした。しばらくの沈黙のあと、彼女は小さな声で呟くように、
「主人は1月4日の晩に亡くなりました………………………………………………………………………………………………………………・・」
「…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………・」
信じたくは無かったが、この一言でロヨラの死を実感せざる得なかった・・・・・・・・。
葬儀は1月7日にしめやかに執り行われ、もう既に墓地に埋葬も行われたそうだった。
「あの感覚は間違いじゃなかったのか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・」
目頭が熱くなり、様々なロヨラへの思いが頭の中を駆けめぐった。
電話を切ったあと、落ち着いたと思ったら、ロヨラの霊を近くに「気」のレベルで感じたので、その時から様々な事をロヨラに語りかけ始めた。
この原稿を書いている時点では、もうロヨラの四九日は一週間後に近づいている。あれから、五月蠅くなるほど掲示板への書き込み・メールが飛び交っていたロヨラの周辺のホームページを覗いてもロヨラ自身の書き込みはなく、何とも言えない寂しさ・悲しさを実感するようになってしまった。
まだ俺自身、気持ちの整理が着いていないせいか、ロヨラに向けての最後の「餞の言葉」が想い浮かばない。生前インターネット上でロヨラと親交があったある方の話によると、ロヨラはもう既に輪廻転生から解脱し、詳しい場所の名前は分からないが、あの世の天使・飛天候補生のような方々が行く場所に居るらしい。そこへ配属された方々は、四九日を過ぎても、自由に現世やいろいろな次元への移動が可能だそうだ。もしかしたら俺や今このホームページをご覧になっている方々の隣に、ロヨラはいるかも知れません。もし来ていたら自然に話をしてやってください。
最後に、ロヨラが彼のホームページで残した最も印象的な言葉を記して、今回は「上書保存」します。”HEART IS GOLD!!”黄金の心を持っていたあの日々に想いを馳せて。
Mr.LOYORA!! Bon Voyage・・・・・。
WOLFIE−JAPAN2003ー2009(C)
◎生きる事(ロヨラのパン「カフェ・ロベルト」より引用)
私は実のところ究極のバカを目指して生きている。究極のバカとは無と有の意味の無くなる状態。神や宗教や生死や言葉の不要な状態。「・」の状態。策略もタテマエも演技も不要であるがままに出来る状態。輪廻も宇宙も無意味となる状態。それを求めて私は手段を選ばず、命への執着もタテマエも捨ててずっと考えて来た。極論を論じて限界の打破を計ったり、感情のみに身をまかせて理性を無くそうとしたり、逆に感情を消そうとしたりして来た。
雑草は雨が降らなければ枯れて死ぬ。人に踏まれても恨まない。ただ生きて、子孫を残し、死が迫れば受け入れる。それこそが自然。あるがままの生。本来の自然の摂理。罪とか、善悪とか、金とか、医学とか、策略等々は本来自然界には無くてもいいもの。
しかし人間は本当の意味ではあるがままに生きられない。文明の発展は自然界の進化ともある意味言える。公害も戦争も地球上の生物である人間が作ったものだから見ようによってはそれも自然と言える。しかし人間は自分の作った悪に対して抵抗している。全て持っているものを手放せばいいのに。そして思考さえも。
雑草もアメーバも文明を持たずに悟りを実践している。雑草に神も宗教も労働も無い。しかし「生きている」しかし人間は苦しみを感じる。悲しみも感じる。無常を感じてもあるがままに生きられず自我意識を保とうとする。
私は雑草になりたい。ただ生きて、ただ死にたい。病気になればそのまま病死してもいい。しかし社会生活をするにはそうはいかない。演技をして生きなければならない。あるがままに生きれば精神病院に戻されてしまう。
だから私は完全なバカを夢見る。
LOYORA 2003(C)
★ロヨラ氏のホームページ
上記のホームページは2003年3月7日時点で開設されているものです。